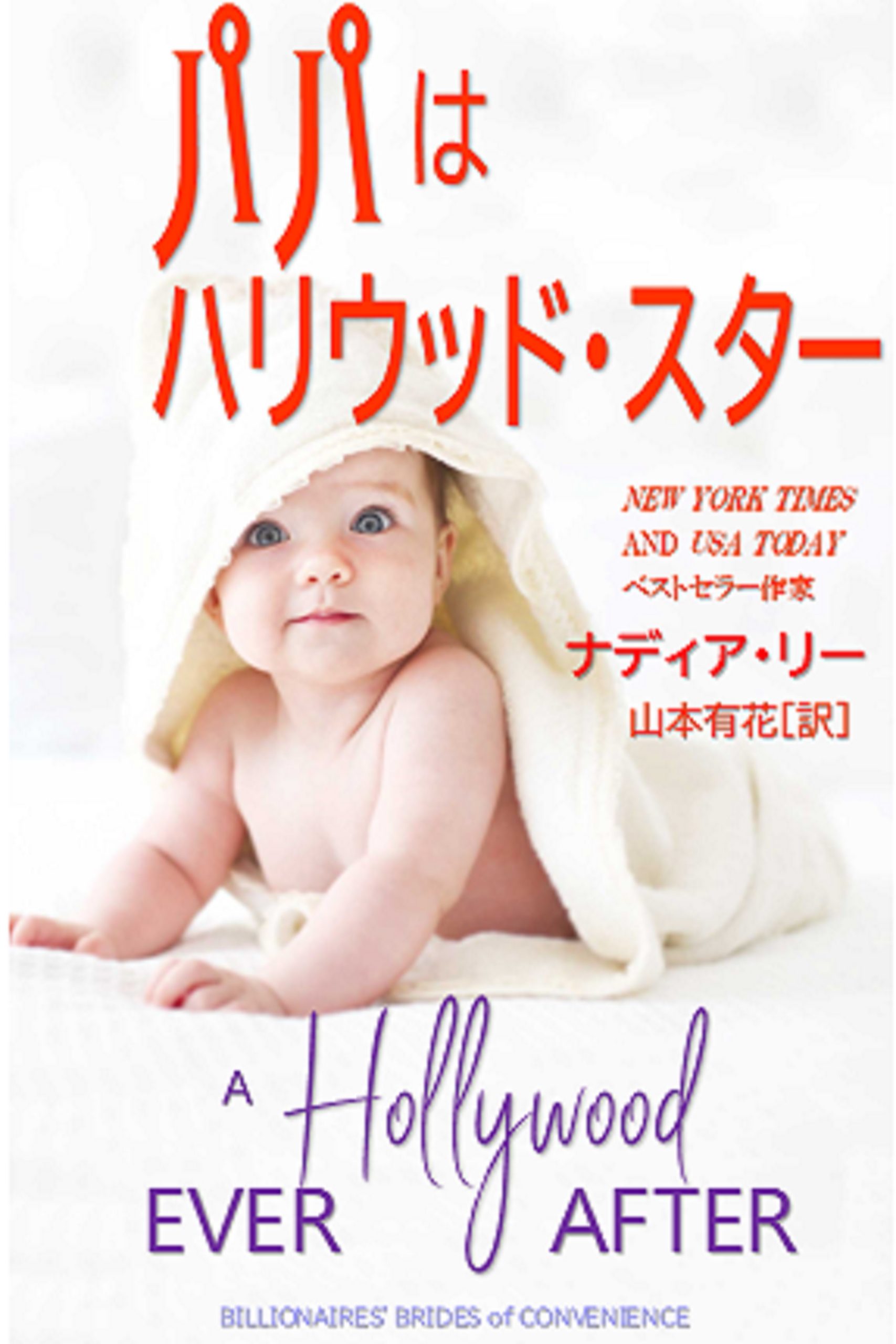「この子はいつになったら生まれてくれるのかしら。早くしないと、そのうち歩けなくなっちゃう」
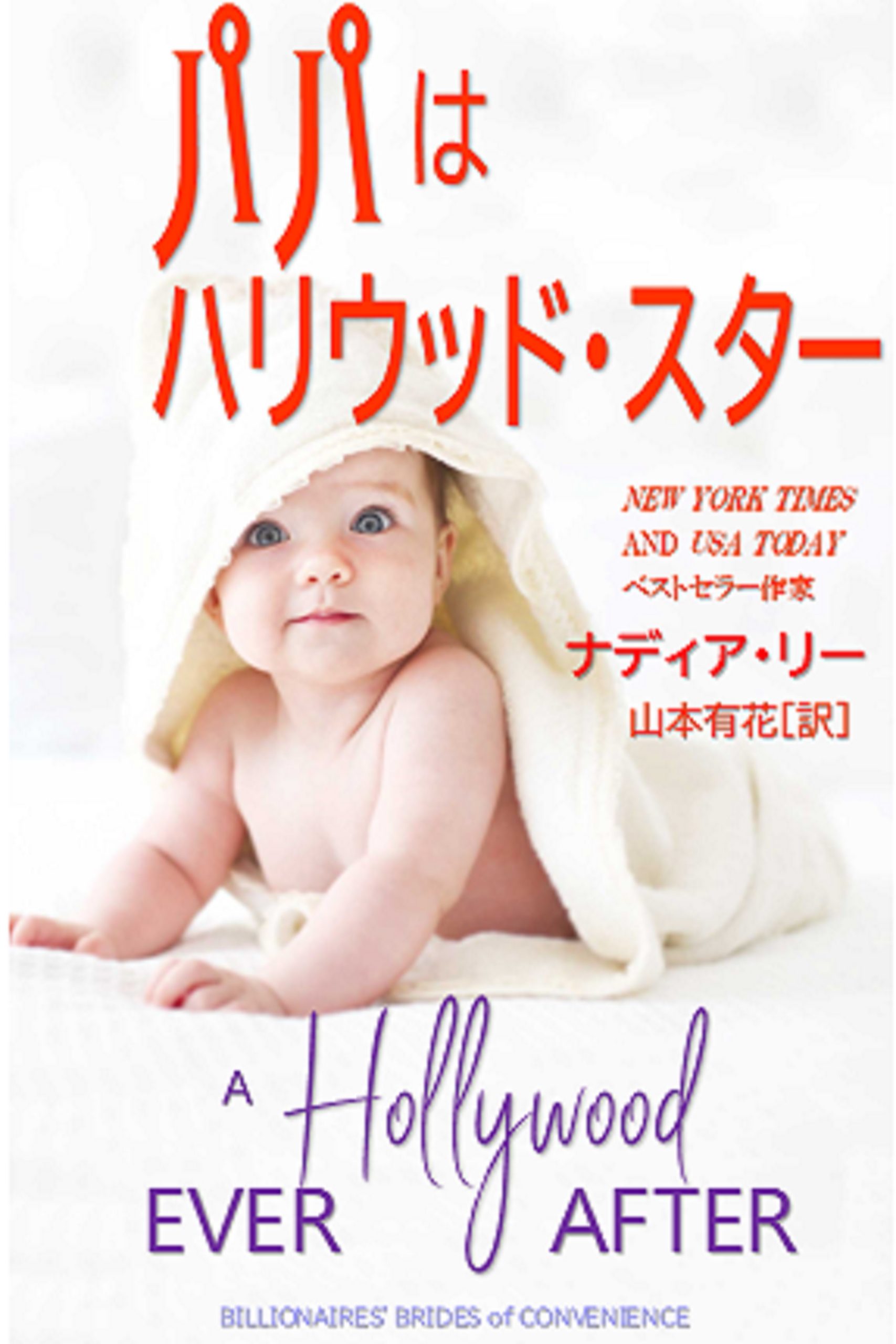
ソファにどっかりと腰を下ろして泣き言を言う私の背中に、ライダーがクッションを充てがってくれた。これがあるのとないのとでは、腰への負担が全然違う。
「予定日はもう少し先だろう? 本人が出てきたいと思うまで待つしかないよ」
彼はそう言って、大きく膨らんだお腹をそっとさすった。
赤ちゃんの性別はまだわからない。エコー検査のときにはなぜかいつもお尻を向けていて、どっちなのか未だにはっきりしないのだ。実際に生まれるまで楽しみを取っておけばいいじゃない、などと言う人もいるけれど、まずベビー服の色を迷う羽目になる。可愛らしい服をいろいろ揃えてあげたかったのに、結局、黄色やクリーム色など、無難な色を選ぶしかなかった。
名前を二通り考えるのも至難の業だ。常に胃が圧迫されて気持ちが悪い上、訳もなくイライラしたり情緒不安定になったりして落ち着かず、候補が全く思い浮かばない。〝出産前セラピー〟なるものがあるなら、是非とも受けたいと思う。この広い大都会、どこかに専門のセラピストがいないものだろうか。
「だけど見て。これじゃあどこに足首があるのかわからないでしょう?」
私は足をちょっとだけ持ち上げてライダーに見せた。
ほんの二か月前までは何ともなかったのに、いつの間にか太くなっていて、今じゃパンパンに張ってしまった。飲んだお水が全部足に溜まっていくような気がして心配になったけど、シルバーマン先生は問題ないと言ってくれた。妊娠後期にはよくあることですよ、あなたは健康体そのものですよと。でも、私に言わせれば、足首がこんなにむくんでいる今の状態は異常としか思えない。
ライダーが私の足首に手を当て、血流を促そうと心臓に向かって優しくさすり始めた。
「仕方ないさ。先生からもホルモンのせいだって言われただろ。でもあんまり辛いなら、妊婦専用のマッサージ師を呼ぼうか? 少しは楽になる」
「うーん、とってもそそられるけど、それより早く出てきてほしい。一時間おきにトイレに行きたくなるし、いつも胃が苦しくてよく眠れないし、いざ眠れそうだと思ったらそんなときに限って遠慮なく蹴ってくるし、ほんと、どうにかなってしまいそう」
「わかるよ。俺だってきみをぐっすり眠らせてあげたい」
彼は身体をずらし、今度は背中を揉みほぐしてくれる。「けどさ、もう少しの辛抱だよ。な? 一緒に乗り越えよう」
この人は本当に優しい。私は床で寝ると言ったのに、ベッドへの乗り降りを手伝うから遠慮しないでと言ってくれたし、夜中にトイレに立つときも途中まで付き添ってくれる。
全身が徐々にリラックスしてきた。
彼の手は魔法の手。どんなにしんどくても、どんなに凝っていても、この手にほぐされると立ちどころに気持ちよくなってくる。些細なことかもしれないけど、こんなふうに気遣ってもらえて、私ほど一人の男性から愛されている女は他にいないんじゃないかと思えてしまう。けれど……、
「ねえ、生まれてくる子があなたの子供じゃないってこと、少なくともご兄弟には前もって知らせておいたほうがいいんじゃないかしら」
そう尋ねてみずにはいられなかった。
「いいや、その必要はないよ。あいつらに事実を告げる義理はないし、俺はきみがつわりで苦しんでるときからずっと一緒にいるんだよ。食べ物の好みが変わったのもこの目で見てきたし、どんどん膨らんでくるお腹をさすり続けたのも俺だ。だから、誰が何と言おうと、父親は俺。その子だって、とっくに認めてくれてるさ。今さら実の父親がしゃしゃり出てきたって関係ないね。それにさ、秘密を知る人間は少なけりゃ少ないほどいいんだ。あいつらに悪気はなくても、いつ、どこで、誰の耳に入るかわからないだろ。メディアに漏れでもしたら、きみたちが嫌な思いをすることになる。場合によっちゃ危険な目に遭わされるかもしれない。そういうのは絶対に避けたいんだよ」